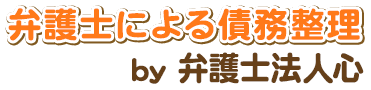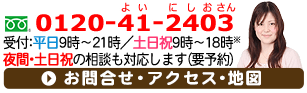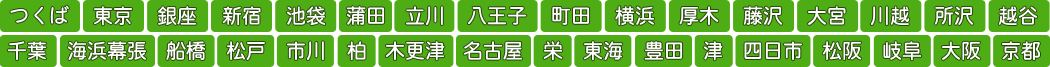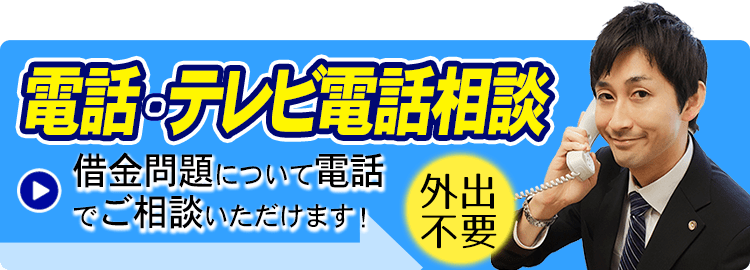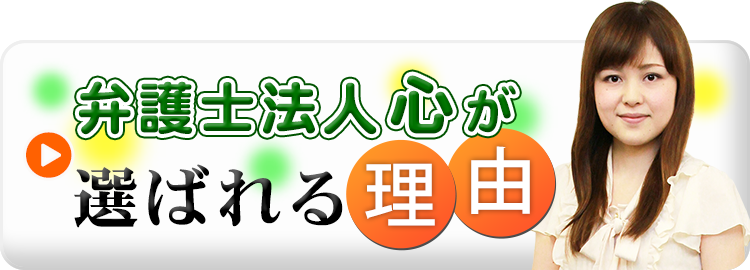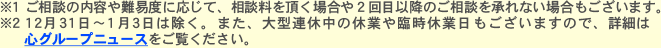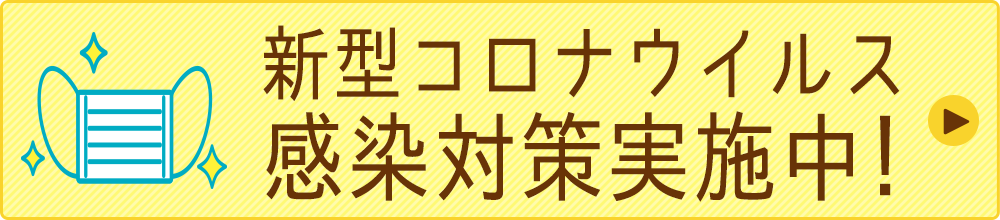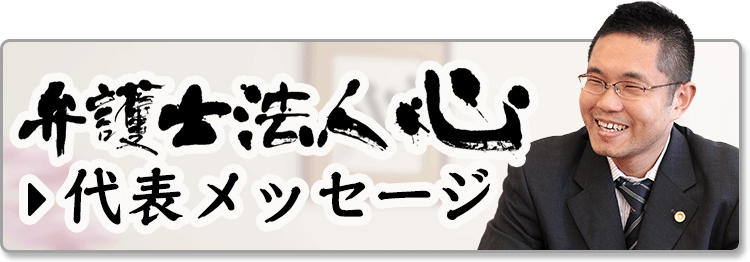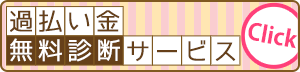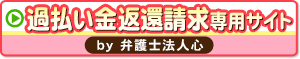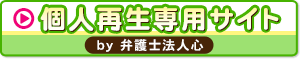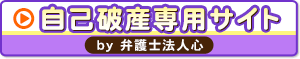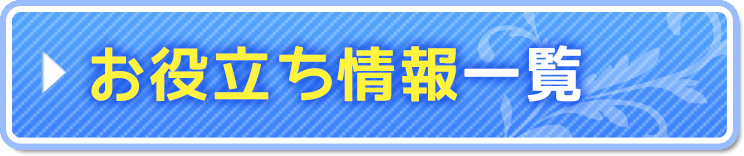任意整理の流れ
1 フリーダイヤル(0120-41-2403)へお電話してください。
債務の状況等の聞き取りをさせていただいた後(詳細な資料は不要です。)、無料相談のご予約を入れていただきます。
2 無料相談
当法人にご来所いただき、弁護士の方から、直接、手続の流れ、解決の見通し、費用等について詳細な説明をさせていただきます。
疑問な点などがありましたら、遠慮なく質問をしていただけます。
債務整理につきましては、依頼者様の意向、債務の内容、生活状況等をしっかり把握しなければ、適切なアドバイスや事案処理が出来ないことなどから、日本弁護士連合会は規程等で、弁護士が債務整理の依頼を受ける際には、依頼者様と直接面談することを義務付けています。
それにもかかわらず、一部の弁護士は、この規定に違反して、電話等のみで、債務整理の依頼を受けているようなので、注意が必要です。
3 手続のご依頼
無料相談の結果、お任せいただけるということになりましたら、弁護士に債務整理をご依頼ください。
その際、費用等の契約内容は契約書の形で明確にします。
4 受任通知の発送
債務整理のご依頼をいただきましたら、弁護士から、貸金業者等に対して、受任通知を発送し、取引履歴(借入・返済の全記録)を取り寄せます。
受任通知の送付により、取立てが止まります。
5 法定利率に基づく引き直し計算
貸金業者等から取引履歴が開示されましたら、法定利率に基づき引き直し計算をし、法律上の正しい本当の債務額、あるいは、過払い状態になっているのであれば、過払い金の額を算定します。
引き直し計算の結果、過払いの状態であることが判明した場合は、過払い金返還請求をしていくことになります。
6 減額交渉等
弁護士が貸金業者等と、利息のカット、元本の減額、出来るだけ長い期間での分割払いになるように交渉し、和解書の形で、弁済金額や弁済方法等を確定させます。
貸金業者ごとに譲歩できるラインがありますので、そのラインぎりぎりまで交渉します。
7 弁済開始
和解書の内容にしたがって、弁済がスタートします。
万が一、途中で、再度、弁済が苦しくなったような場合には、再交渉いたしますので、必ず、ご相談ください。
※弁護士法人心では、ご依頼中に、万が一、担当弁護士や担当スタッフに言いづらいようなことがございましても、担当弁護士等から独立した機関として設置された「お客様相談室」にお気軽にご相談いただくことが出来ますので、より安心です。
複数の事務所があります
各地お越しいただきやすい場所に事務所を設置しております。事務所までの詳しい地図もご覧いただけますので、ご来所の際は参考にしていただければと思います。