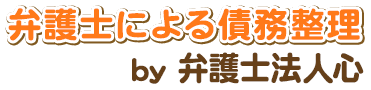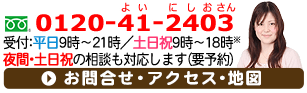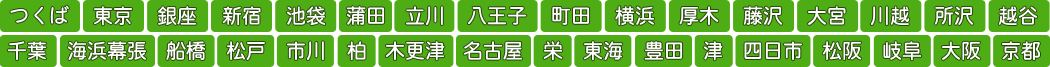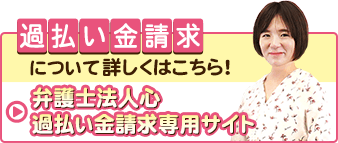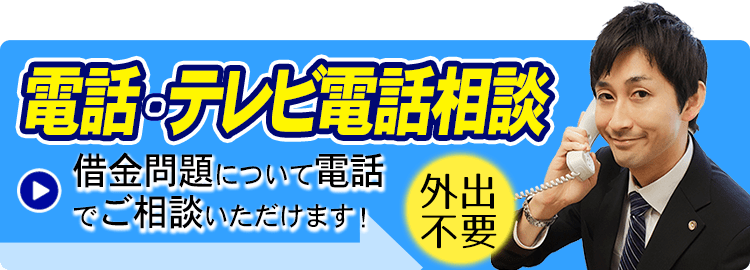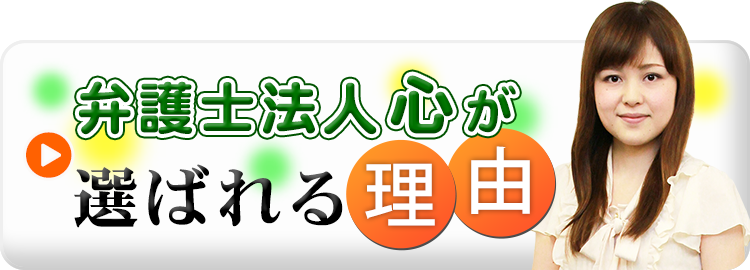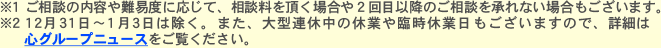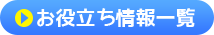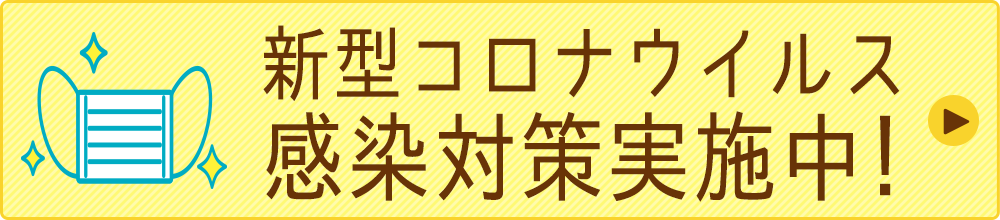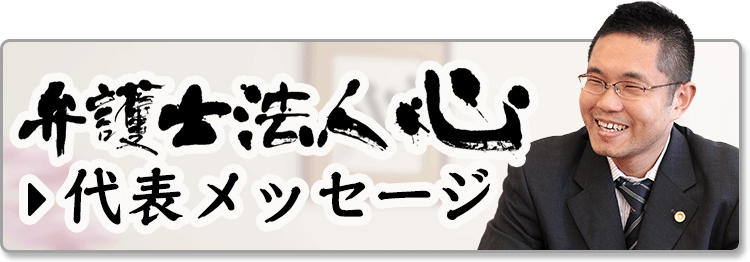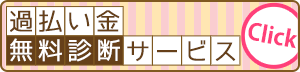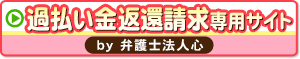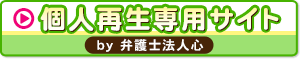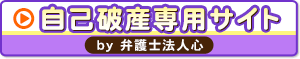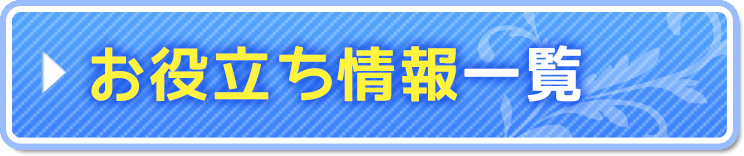過払い金返還請求のご相談をお考えの方へ
弁護士法人心では、過払い金に関するご相談を原則相談料・着手金無料で承るとともに、過払い金額を無料で診断させていただくサービスも行っております。
債務整理を検討されている方の中にも、長期間にわたり取引を行っているなど過払い金が発生している可能性がある方は多いかと思います。
弁護士法人心まで、お気軽に相談ください。
地図等をご覧いただけます
弁護士法人心は、名古屋駅からのアクセスがとてもよい法律事務所です。また、付近の駐車場をご利用いただくこともできますので、お車でのご来所も可能です。
過払い金の相談に必要となる資料
1 はじめに

過払い金とは、テレビCM等で耳にしたことがあるかと思いますが、過去に利息制限法で定められた以上の高い金利で消費者金融等からお金を借りていた方が、払いすぎていた利息の返還を受けるものです。
平成18年頃までに借入を始めた方であれば、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金の相談をする際には、どのような資料が必要となるのでしょうか。
2 基本的に過払い金の相談に資料は必要ない
お手元に何も資料が無いという方でも過払い金の請求は可能です。
しかし、相手の業者名が分からないことには打つ手がありません。
完済から何年も経って失念していたり、亡くなったご家族の過払い金請求を行うケースでは、当時の請求書や振込明細を探したり、通帳に業者名の入出金の記録がないかを調べたりします。
曖昧でも業者名を思い出すことが出来れば、取引履歴の開示請求を行うことで、過去の取引の有無が分かります。
3 過払い金が発生しているかを調べるには取引履歴が必要
過払い金の相談をされる方が一番知りたいのは、過払い金がいくら発生しているのか?ということでしょう。
過払い金の金額は、「取引履歴」という、いついくら借り、いついくら返したかという履歴をもとに、利息制限法で定められた利率に直して計算し直す「引き直し計算」を行うことで分かります。
取引履歴は、相手の業者に開示を求めれば発行してもらうことが出来る書類であり、ご本人様でも取得が可能です。
4 カードや契約書があると裁判で有利になることもある
過払い請求では、相手の業者と任意で交渉を行って和解するケースが多いですが、途中で長期間取引がない期間がある等で過払い金額が争いとなれば、裁判をして過払い金を回収するケースもあります。
当時のカードや契約書があれば、裁判で証拠として提出することで、こちらに有利になる可能性があります。
5 まずはご相談を
たとえ過払い金が発生していたとしても、一般的に完済から10年経過すると時効で消滅し、請求できなくなります。
令和2年の民法改正以降に完済をされた方の場合は、ご事情にもよりますが、完済から10年のほか、権利行使できることを知った時から5年でも時効で消滅するおそれがあるため、さらに早く対応をする必要があります。
何も資料が残っていなくても、過払い金の調査や請求は可能ですので、時効となって後悔する前にお早めにご相談ください。
過払い金の計算方法と具体例
1 過払い金とは
過払い金とは、法律で認められているより高い利息を払っていた場合に、法律で認められた上限の利率に引き直して計算して、払いすぎた利息のことです。
ここでは、具体的に過払い金がどう計算されるか見てみましょう。
2 上限利率18%に対し、25%で借り入れた例

たとえば、平成15年1月1日に50万円を年利25%で借り入れ、2月1日に5万円返し、同じ日に年利25%で50万円借り入れ、3月1日に97万8031円返したとします。
法律で認められた利率は年18%(1年間で元本の18%まで利息がとれる)です。
これは、利息制限法で、元本額が100万円以上なら15%、10万円以上100万円未満なら18%、10万円未満の場合は20%を上限とすると定められているからです。
それにもかかわらず25%という高い利率でお金を借りていたので、利息の払い過ぎが発生するわけです。
3 25%のシュミレーション
50万円を年利25%で借りると、1月1日から2月1日(初日は含まない)で1万0273円(50万×0.25÷365×30日)の利息がつきます。
5万円返済すると、元本を3万9727円返済する(5万-1万0273)ので、2月1日時点の元本が96万0273円(50万-3万9727+50万)になります。
3月1日までに利息が1万7758円(96万0273×0.25÷365×27日)つきますから、97万8031円(96万0273+1万7758)払って完済、つまり債務額0になります。
4 18%のシュミレーション
50万円を年利18%で借りると、1月1日から2月1日で7397円(50万×0.18÷365×30日)の利息がつきます。
5万円返済すると、元本を4万2603円返済する(5万-7397)ので、2月1日時点の元本が95万7397円(50万-4万2603+50万)になります。
3月1日までに利息が1万2747円(95万7397×0.18÷365×2
7日)つきますから、97万8031円払うと、(97万8031-95万7397-1万2747)7887円払い過ぎの利息が発生します。
5 まとめ
過払い金は、払いすぎた利息が元本に充てられて、元本が減るのがポイントです。
例はたった2ヶ月の取引なので約8000円ですが、これが20年続くと大きな金額になってきます。
過払い金返還請求について専門家を選ぶ際のポイント
1 専門家の種類 弁護士に頼むか司法書士に頼むか

司法書士に過払い金返還請求を依頼することもできますが、それは一定の場合に限られます。
司法書士は、140万円以上の案件については代理することができないので、金額が大きくなる可能性がある場合には、弁護士に依頼した方が無難です。
140万円以上の場合には、本人が書類を作成したという形式で過払い金の返還請求をすることもあるようですが、代理を依頼する場合に比べて本人の負担が重くなることが多いです。
また、140万円以下の場合でも、控訴等の上訴がなされた場合には代理権を失うので、仮に金額が大きくない場合でも弁護士を選ぶ方が無難といえます。
2 報酬が分かりやすいかどうか
通常、過払い金の報酬は、回収した金額のパーセンテージで決められることが多いですが、それ以外の手数料等を請求する事務所も存在します。
手数料の金額や定め方によっては、思わぬ高額報酬になることもあるので、どの程度の報酬がかかるかは事前によく確認した方がよいでしょう。
3 裁判をすることに消極的でないかどうか
過払い金については、細かい争点等は多々あり、きちんと回収するには裁判をすることが必要になることもあります。
短期(2~3か月)での回収をするためには、裁判をしないことを前提としている可能性があります。
そのため、しっかりと過払い金を回収したい場合には、避けた方が無難かもしれません。
4 当法人へのご相談
このように、過払い金返還請求については、報酬が明確で、裁判をするのに消極的でない事務所を選ぶべきだと思います。
当法人では、相談料・着手金は0円、成功報酬は過払い金回収額の19.8%(税込。実費等は別途)で対応しており、裁判についても数多くの実績があります。
名古屋近郊にお住まいで、過払い金返還請求をお考えの方は是非、お気軽にご相談ください。
過払い金が発生する可能性がある人はどういった人か
1 消費者金融かクレジットカード会社から借入をしていたこと

過払い金は、利息制限法が定める上限金利(限度枠の大きさによって15~20%)を超える金利で借入と返済をしていた方が、払いすぎた利息を取り返す手続きです。
利息制限法とは、お金を貸す際に守る必要のある法律です。
改正貸金業法が完全施行されるまでの出資法による上限金利は、29.2%とされていました。
29.2%を超えた利率の場合、刑事罰の対象となります。
つまり、利息制限法の上限金利を超えているだけで、出資法の上限金利を超えていないような場合には、刑事罰は課されませんでした。
この利息制限法と出資法の間の金利をグレーゾーン金利と呼び、グレーゾーン金利でお金を借りている場合に、過払い金は発生します。
上限金利を超える金利で貸し付けを行っていたのは、消費者金融やクレジットカード会社です。
そのため、銀行からの借入や住宅ローン、車のローン等しか借入をしたことがない方は過払い金が発生しません。
また、貸金業者の中には、利息制限法内の利率で貸金をしている業業者もいるため、すべての業者が該当するわけではありません。
そこで、過去に消費者金融かクレジットカード会社からショッピングではなくキャッシング(お金を借りる)していた方か、現在消費者金融かクレジットカード会社から借入している方が対象になります。
2 おおむね平成19年以前から借入をしていたこと
過払い金は、平成18年1月13日最高裁判決で、これまで貸金業者が有効と主張していたみなし弁済が、原則として否定されたことで、請求する方が増えました。
この判決を受けて、貸金業者は、平成19年頃から高すぎる利率を利息制限法が定める上限金利以下に引き下げるなどの対応をとるようになりました。
このため、平成20年以降から借入を始めた人は、過払い金が発生しないのが通常で、逆に平成19年頃以前から借入をしていた人が、過払い金の発生の可能性がある人ということになります。
3 完済から10年(あるいは5年)経過していないこと
過払い金は、完済から10年たつと、時効によって消滅し、返還してもらえなくなります。
令和2年の民法改正後に完済した場合は、完済から10年、または権利行使できることを知った時から5年たつと、時効によって消滅します。
完済から10年、あるいは5年たっていない人が、過払い金が発生する可能性がある人ということになります。
ショッピングは利用し続けているがキャッシングは完済してから10年たっているという方は、先ほどの過払い金があるのはキャッシングであるという原則により、時効で過払い金を返してもらえない可能性が高いです。
そこで、キャッシングの完済から10年たっていないことが必要になります。
時効に関しては、ご事情によって、実は過払い金を主張できたというケースもあるため、弁護士に判断してもらうことをおすすめします。
4 一度弁護士におたずねください
過払い金が発生している可能性がある人は、主に平成19年以前から消費者金融又はクレジットカード会社のキャッシングを利用していた人で、キャッシングの完済から10年(あるいは5年)たっていない人ということになります。
過払い金は、お金を高い金利で借り、実際には支払う必要のなかったにもかかわらず、支払っていたお金です。
もし過払い金が出れば、今もある借り入れの返済に充てたり、お金が戻ってくることができます。
該当するか分からないという方は、お問い合わせだけなら無料ですので、一度弁護士までおたずねください。
過払い金返還請求は裁判をするのですか
1 過払い金返還請求は裁判をしないで解決することも多い

過払い金返還請求をすると、まずは業者と返還する過払い金の額と返還時期を交渉します。
この交渉がまとまらなければ裁判を起こすことになりますが、交渉がまとまることも多いです。
交渉がまとまれば、通常、業者との間で返還金額や返還期限、返還期限に入金が遅れた場合の損害金等を記載した和解書を取り交わし、返還期限までには弁護士の口座に入金がなされます。
2 裁判を起こすメリット
裁判所の間で判断が分かれるような論点がなくても、基本的に、業者は過払い金全額を返還するとは言ってきません。
交渉段階では過払い金の元金の7~8割程度以下を返還するとの条件での和解しか提案してこないことが多いです。
ですので、このような場合には、裁判を起こすことで、業者からより高額の和解の提案を引き出したり、裁判所から過払い金全額の返還を認める判決をもらったりすることができます。
3 裁判を起こすデメリット・リスク
裁判を起こす場合、別途、裁判費用(印紙代、切手代等)がかかりますし、相手方が争ってきたら解決までに長期間を要します。
また、業者の反論が裁判所に受け入れられることもあり、交渉段階で提案されていたよりも低い金額で判決が下る可能性があります。
時間や費用をかけてでも判決を取得する利益があるかを弁護士と協議することになります。
さらに、非常に稀ですが、取引の経緯等について借主ご本人が裁判所に呼び出され、説明を求められるケースも存在します。
4 ご相談は過払い金返還請求の経験が多い弁護士へ
裁判を起こした方がよいか否かを判断するには、どのような判決が下されるかについての見込みの正確性が重要となります。
そのためには、相手方の反論がどの程度裁判所に認められる可能性があるかや、業者ごとの特性についての深い知識・経験が必要です。
弁護士法人心では、過払い金返還請求も含めた債務整理分野に特化した弁護士がチームを組んで研鑽を重ね、裁判による解決も含めて多額の過払い金を回収してきました。
過払い金返還請求をお考えの方は、弁護士法人心岐阜法律事務所までお気軽にご相談ください。
過払い金返還請求は弁護士へ
1 弁護士と司法書士

過払い金返還請求について専門家に依頼する場合、弁護士または司法書士(簡裁訴訟代理業務を扱える認定司法書士)が候補になります。
ただし、司法書士が代理人として交渉や訴訟を行うことができるのは、簡易裁判所の管轄となる140万円以下の案件に限られます。
しかし、過払い金返還請求の相談をする段階では、過払い金の金額は不明であることが通常ですので、まず、どちらの専門家に相談すればよいのかが問題になります。
2 相談は弁護士へ
⑴ 自宅の近くに認定司法書士の事務所はあるが、弁護士事務所はない場合、とりあえず司法書士に相談してみるのもよいと思いますが、過払い金返還請求の場合、法律相談に行った際に過払い金返還請求を依頼すれば、その後はメールや電話でやり取りを行いますので、2回、3回と事務所に行く必要はありません。
そのため、自宅から近いことを理由として司法書士事務所を選択するというのは、それほどのメリットにはなりません。
⑵ 過払い金の金額は、消費者金融会社やクレジットカード会社から取引履歴を取り寄せ、それを基にエクセル等を利用して計算することによってようやく判明します。
もちろん、消費者金融等との取引期間や極度額についての情報があれば、過払い金返還請求事件を多く扱っている専門家であれば、だいたいこれくらいの金額だろう、という予測をすることはできますが、一般の方の場合、その予測は困難です。
仮に司法書士に依頼し、利息制限法の上限利率で再計算した結果、140万円を超えていた場合は、交渉や訴訟の代理は弁護士に依頼しなければならず、手間が増えることになります。
そうであれば、最初から弁護士に相談する方が手間はかからない、ということになります。
3 140万円以下でも弁護士へ
もし、相談前にご自身で過払い金の計算を行い、金額が140万円以下であることが判明していたとしても、弁護士への依頼をお勧めします。
例えば、取引の分断などの争点があるため交渉がまとまらず、訴訟を提起したものの、第1審の簡易裁判所でも敗訴した場合、さらに争うためには地方裁判所に控訴しなければなりません。しかし、司法書士は地方裁判所の代理権を有しませんので、控訴審には依頼者ご本人が出廷する必要があります。
弁護士であれば、当然ですが控訴審でも代理人として訴訟活動ができますので、依頼者ご本人が出廷する必要はありません。
過払い金返還請求については、弁護士も司法書士も報酬はほとんど変わらないと思われますので、そうであれば、控訴審も考慮し、最初から弁護士に依頼するのがベストです。
過払いの受任通知と信用情報
1 債務整理の受任通知

⑴ 弁護士が任意整理、個人再生、自己破産の依頼を受けると、銀行や消費者金融、クレジットカード会社などの債権者(任意整理の場合はその対象とする業者)に受任通知を発送します。
受任通知には、自己破産等について委任を受けた旨と、債務者(依頼者)への直接の連絡を停止するよう要請する内容を記載します。
⑵ 債務整理の受任通知を受領した金融機関は、弁護士が債務整理で介入した事実を信用情報に登録します。
これが事故情報と呼ばれる情報です。
ある債務者について貸付けやクレジットカードの発行を行った金融機関は、その債務者の信用情報を定期的にチェックしていると言われていますので、事故情報が登録されると、任意整理で債務整理の対象としなかったクレジットカード会社のカードも通常、しばらくすると使えなくなります。
2 過払いの受任通知
⑴ 利息制限法の制限利率を超える利率での借り入れと返済を繰り返していた場合、利息制限法の制限利率で計算し直すと借金は消滅し、過払い金が発生することがあります。
この場合において、消費者金融については借り入れをすべて返済しており、またクレジットカード会社については借り入れもショッピングの負債もすべて返済しカード契約を解約しているケースでは、弁護士が業者に送付する受任通知は過払い金返還請求を内容とするものになり、いわゆる債務整理の受任通知とは異なりますので、信用情報に事故情報が登録されることはありません。
⑵ しかし、約定利率による債務が残っている場合、仮に利息制限法の制限利率により計算し直すと過払いになっていたことが判明した場合でも、弁護士が任意整理(または過払い)の受任通知を送付した時点でいったん事故情報が登録されることになります。
その後、過払い金返還請求について和解等で解決すると、債務は完済となりますので、その旨が登録されますが、いったん事故情報が登録された影響は任意整理と同様に一定期間継続します。
⑶ そこで、過払いがあるかどうかを調べたいという場合は、業者からキャッシングの取引履歴のみ請求し、返済はそのまま継続しておく必要があります。
債務整理について詳しくない弁護士に依頼すると、間違えて任意整理の受任通知を送付してしまい、事故情報が登録されてクレジットカードが使えなくなってしまうということもあり得ますので、依頼する際は、ご自身の要望を明確に弁護士に伝えることが重要です。
過払い金返還請求は家族に知られずにできますか
1 貸金業者や裁判所等から連絡が来ることはほとんどありません

ほとんどの場合、当法人にご依頼いただければ、ご家族や勤務先等には全く知られずに過払い金返還請求を行うことができます。
過払金返還請求をご依頼いただいた場合、貸金業者に代理人になったことを告げる受任通知を送ることになりますが、そこに本人等に直接連絡しないようにするよう求め、仮に本人やその家族に連絡したような場合には、損害賠償請求等を行う旨を記載しています。
これにより、弁護士に過払金返還請求を依頼したことによって、貸金業者が依頼をした本人やその家族に連絡することを防ぐことができます。
また、裁判等を起こす場合も、裁判所に対して連絡先を当法人に指定しますので、裁判所から連絡が来ることもありません。
したがって、過払い金返還請求を進めていくためのやり取りは当法人とのやり取りに限定されることになります。
2 当法人からご家族等に過払金返還請求したことが漏れることはありません
当法人とのやり取りについては、連絡方法を指定していただくことも可能です。
連絡方法についてメール等に限定し、書類等については、事務所にお越しいただいた際に、直接書類をお渡しするような形で進めていくことも可能です。
したがって,ご家族に過払金返還請求をしていることを知られるきっかけはほぼないことになります。
3 気を付けなければならない業者も把握しています
ただ、少数の特殊な業者については、ご家族等に知れるようなきっかけを意図的に作出することもあります。
ただ、そのような業者は少数ですし、特定されているので、事前に対策をとることが可能です。
4 まとめ
以上のとおり、過払金返還請求については、ほとんどの場合、ご家族に知られずに手続きをしていくことが可能です。
10年以上前から消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングの取引があるよう場合には、ぜひお気軽にご相談ください。
過払金返還請求における争点
1 完済による取引の分断

これは、最もポピュラーな争点の一つです。
過払金がある方は、長年貸金業者からの借入と返済を繰り返していることがほとんどです。
その過程の中で、残元金が0になった日(完済した日)があり、その後また借入をしているということがあります。
このような場合、貸金業者側は、完済前の取引と、再度借入をした後の取引は別々の取引であるという主張をすることがあります。
取引が分断することで、次のような主張につながります。
すなわち、一度完済した日が10年以上前である場合、完済前に発生していた過払金は時効によって消滅するという主張をします。
もちろん、こちらもこの主張をそのまま受け入れることはなく、反論します。
取引が分断されたといえるか否かは、完済後次の借入までの期間、利率等の契約内容の変化、カードや契約書の返還の有無などを総合考慮して判断されることになります。
そこで、訴訟等において、具体的な分断期間や、契約番号の変化の有無等について再反論し、一連一体の取引である旨を主張します。
2 悪意の受益者性
取引の分断と並んで、貸金業者からよく主張されるのが、悪意の受益者性に関するものです。
貸金業者側は、悪意の受益者ではないということを主張してきます。
過払金の返還を請求する権利は、法律的には不当利得返還請求権という権利です。
訴訟によって過払金の返還請求を行う場合、過払金の元金に、完済の日の翌日から支払済みまで年5%の利息を付けて支払うよう請求することができます。
この5%の利息の請求は、被告である貸金業者において、法律上受け取ってはいけない金銭であると知っていた場合に請求することができます。
法律上受け取ってはいけないことを知りつつ、受け取った者のことを、「悪意の受益者」といいます。
制限利息以上の利息を受け取っていた貸金業者はプロであり、利息制限法の制限を超えていることを通常知っているので、ほとんどの場合これに当てはまります。
ところが、多くの貸金業者は、このことを争います。
なぜなら、完済の日の翌日から支払済みまで年5%の利息というのは、貸金業者側から見ると非常に大きな負担になりうるからです。
仮に9年前に完済していたとしたとします。
ここに年5%の利息が加わると、元金の45%の利息を支払うことになりますので、貸金業者側が支払う金額は大幅に増えることになります。
貸金業者の主張が認められることは多くはありません。
もっとも、貸金業者側もビジネスの世界で生き残るため、新しい理論を産み出しては主張してきます。
当法人の弁護士は、最新の動向を研究し、再反論によって過払金の支払いを認めてもらう技術を日々研究しています。
過払い金返還請求をお考えの方へ
1 完済過払と残有過払の流れの違いについて

過払金の請求をする際に、すでに債務を完済した状況で請求をする場合には、信用情報が傷つく心配なく、弁護士に依頼していただいて、取引履歴の開示請求をすることができます。
他方で、まだ借金の返済をしている途中で(いわゆる「残あり」)、「ずいぶん長い間、借金を返済してきたので、過払金が発生しているのではないだろうか?」と思った場合には、そのタイミングで、弁護士をとおして貸金業者に取引履歴の開示請求を行うと、借金の返済を約定どおりしない宣言と受け取られてしまい、信用情報に事故情報として掲載される恐れがあります。
この場合には、弁護士を通さずに、自分自身で取引履歴の開示を請求し、開示された取引履歴を持って弁護士事務所までご相談に来ていただくという方法が考えられます。
この方法であれば、信用情報に傷がつくリスクを回避しながら、現時点での過払金の有無や見込み額をチェックすることが可能になります。
2 取引履歴の開示義務を貸金業者が負っていること
なお、「取引の履歴なんて、業者が出してくれるのだろうか?」とご不安に思われる方もいるかもしれません。
この点について、貸金業法という貸金業者が従うべきルールを明確にした法律の19条の2では「債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。」と定めています。
そして「前条の帳簿」とは、貸金業法19条に「貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と定められているとおり、「契約年月日、貸付の金額、受領金額その他」の記載された帳簿のことであり、まさしく取引の履歴のことです。
このように、貸金業法では、債務者から請求があった場合には、原則として、貸金業者は取引履歴の開示をすることを義務付けていますので、自信をもって取引履歴の開示を請求していただいて問題ありません。
3 まとめ
取引履歴の開示ができましたら、具体的に過払金が有るのか無いのかや、どのくらいの金額が見込まれるのかなどの具体的な計算にうつらなければなりません。
この点の判断については、法的な知識も必要となってまいりますので、もし、名古屋で過払金の請求をお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、弁護士法人心までご相談ください。
過払い金返還請求を弁護士に依頼する場合の直接面談義務
1 過払い金返還請求ができる場合

過払い金とは、簡単にいうと、借主が貸金業者等の貸主に返済しすぎたお金です。
利息制限法に定める上限利率を超える高い利率でお金を借りていた場合に、利息が払いすぎになっていることがあります。
この払いすぎた分が過払い金です。
2 直接面談の義務化
弁護士が債務整理をするにあたって、日本弁護士連合会規程によって、受任弁護士が債務者に自ら個別に面談して事情聴取をすることが、原則として義務付けられています。
この弁護士との面談の義務を、直接面談義務といいます。
3 直接面談義務の目的
弁護士が一度は直接面談して事情聴取を行うことで、ご相談者様と弁護士の間の認識のズレが生じることを防止することや、責任の所在を明確にするために、この直接面談義務が定められています。
ただし、例外として、「面談することに困難な特段の事情」がある場合直接面談義務が免除される場合があります。
4 過払い金の直接面談義務
この直接面談義務は、債務がある場合にのみ適用されます。
そのため、まだ借金を完済していない場合に過払い金請求をしたいというご相談の場合には、直接面談義務があります。
他方、すでに借金を完済している場合は、直接面談を行う必要はなくなります。
5 完済過払以外は直接面談を守っている弁護士に相談すべき
直接面談義務は、ご依頼者様の利益を守るために、弁護士会の規則で定められています。
借金を完済していない状態にも関わらず、直接面談をしようとしない弁護士事務所には注意が必要です。
弁護士に過払い金の相談をする場合は、直接面談義務を守っている弁護士に相談することをお勧めします。
他方、完済過払については、電話やテレビ電話でのご相談で移動の時間をかけずにご対応させていただきます。